|
広い面積の大陸棚や流量の大きな河川などのおかげで、東シナ海は栄養に恵まれた豊かな漁場となっています。魚、イカ、エビなどのふるさとで、ここで生まれた魚たちの多くは黒潮や対馬暖流によって本州南方海域や日本海に運ばれます。ところが、東シナ海においても、人間活動による地球温暖化や環境負荷の問題が心配されています。このような背景をもつ東シナ海の漁場の環境について、どのような仕組みで環境に変化が生じ、その結果、魚たちがどのような影響をうけるかを明らかにするため、調査や研究を行っています。
|
|
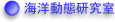 |
|
|
沿岸の漁場や沖合の漁場の水温、塩分、流れの状態が変化していく様子、変化する仕組みなどを解き明かすことと、それらが将来どのように変化していくかを予測するための調査研究を行っています。
|
|
 |
|
|
沿岸の漁場や沖合の漁場の海水に含まれる栄養塩がどのようにして作られ、またこの栄養塩を利用して植物プランクトンがどのように増えるのかの仕組みについて、水温や太陽の光の強さなども測りながら調査研究を行っています。
|
|
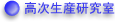 |
|
|
魚などはいろいろな生物を餌として食べていますが、その餌となっている生物(おもに動物プランクトン)の種類、量、生まれてから死ぬまでの生活の様子や魚などとの関係について調査研究を行っています。
|
|



