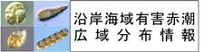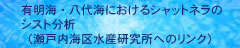海藻・藻場に関する情報
長崎市沿岸で見られる南方系ホンダワラ類の暫定的分類基準
海の中にも森があります。沿岸の浅瀬に形成される海藻の群落のことで、藻場と呼ばれています。この藻場は、アワビやイセエビなど多くの水産資源や沿岸生態系の多様性を支える重要な環境要素です。しかし、長崎市周辺の藻場は衰退傾向を示しており、各地の漁業者の皆さんは危機感をつのらせています。
衰退の最もひどい場合が磯焼けと呼ばれるもので、海底に直立する海藻が全くなくなります。このような量的な変動に加えて、従来ほとんど見かけなかった南方系(暖海性)ホンダワラ類と呼ばれる海藻が増えており、藻場は質的な変動も見せ始めています。これらの海藻がなぜ増えてきたのか、沿岸生態系においてどのような存在なのかなど、様々な研究を早急に進めなければなりません。
しかし、これらの海藻については分類学的な検討が遅れており、種名さえはっきりしないものが多いのです。様々な研究・調査を進めるには、まず種を識別することが何より重要ですが、そこに大きな壁が立ちはだかっています。
そこで、この問題解決の一助となるよう、下表の海藻や藻場に詳しい研究者によって、平成18年度西海区研究所所内プロジェクト研究が実施されました。この研究では、2006年7月上旬に長崎市見崎町地先において標本採集と水中観察を行い、従来の分類学的基準や生態的基準に基づいて、それらの暫定的な分類基準を作成しました。この基準は、沖縄県から鹿児島県に至る水域において、南方系ホンダワラ類の分類学的研究を進めている鹿児島大学(現、瀬戸内海区水研)の島袋寛盛氏による分類基準をベースにしたもので、さらに北海道大学名誉教授の吉田忠生先生が文献学的見地による検討を加えられました。(2007年3月作成版)
その後、さらに分類基準の再整理をすすめるために、九州や南西諸島でホンダワラ類を採集し、外部形態やDNA塩基配列を比較したり、過去に作成された標本に検討を加え、現在の様な分類基準に至りました。この改訂作業の詳細は、【分類チャート】のページに記されています。(2010年5月更新版)
なお、標本の採集と現地調査においては、新三重漁業協同組合の皆様のご理解とご協力を賜りました。この場を借りて、お礼申し上げます。
本HPを、南方系海藻に関心や興味をお持ちの皆様にご利用いただければ幸いです。ご覧いただいた皆様との情報交換や議論を通じて、適宜更新や追加を進めていきたいと考えております。ぜひ、ご意見や情報を下記までご一報ください。
連絡先 : 西海区水産研究所 業務推進課 電話:095-860-1600(代表)
2010年2月更新

長崎県見崎地先の在来種(アカモク、マメタワラ)と南方系種(キレバモク)の混生群落
| 平成18年度西海区水産研究所所内プロジェクト研究 「九州・山口地域における藻場の変動に関する基礎的研究」 参加メンバー | |
| ・鹿児島大学大学院(現、瀬戸内海区水産研究所) | 島袋 寛盛 |
| ・北海道大学名誉教授 | 吉田 忠生 |
| ・鹿児島県水産技術開発センター | 田中 敏博 |
| ・長崎県総合水産試験場 | 桐山 隆哉 |
| ・海中景観研究所株式会社 | 新井 章吾 |
| ・西海区水産研究所 沿岸資源研究室 | 吉村 拓 |
| ・ 〃 | 清本 節夫 |
| ・ 〃 | 八谷 光介 |